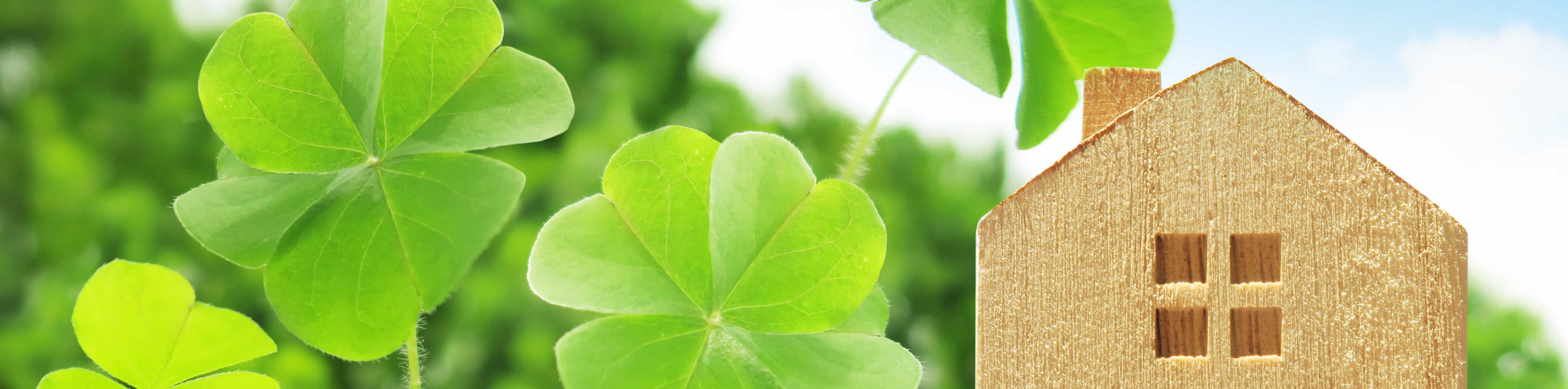
出前講座
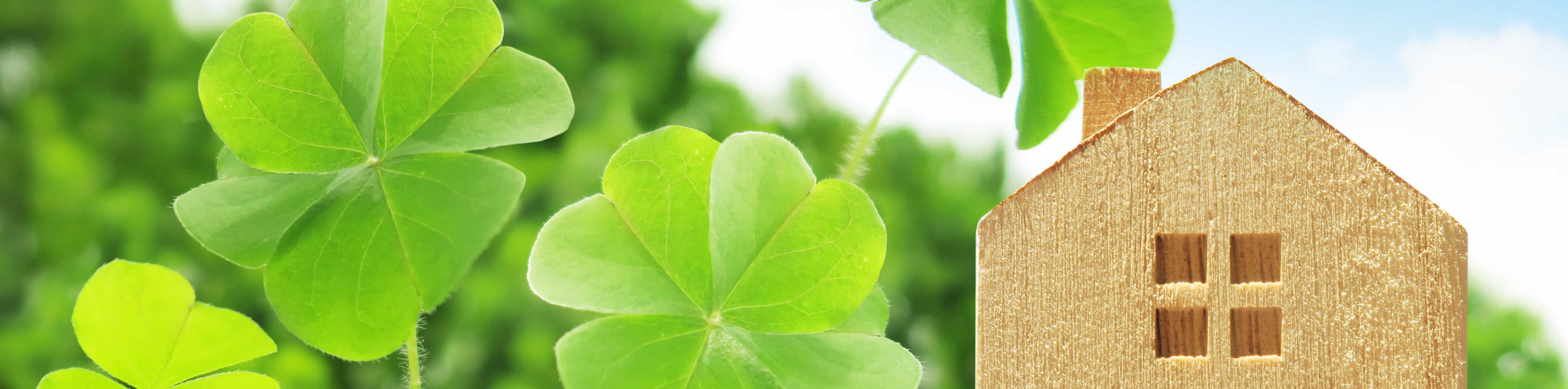
出前講座
高崎市医療介護連携相談センター南大類の特徴を活かした出前講座をおこなっております。
医療介護分野の学習に、この出前講座を活用していただけると幸いです。詳しくは、下記をご参照ください。皆様からのご依頼をお待ちしています!!
医療介護専門職の皆さまの医療介護福祉分野の知識の向上のため。
要望に応じて、勉強会の講師を派遣する。
高崎健康福祉大学 4学部7学科の教員(※テーマ一覧参照)
高崎市のケアマネジャー、介護職、医療介護専門職者 等(10名以上の参加者で実施が可能です。)
※高崎市以外からの依頼者は、別途料金、交通費のお支払いをお願いします
高齢者あんしんセンター、福祉施設、医療機関等事業所と大学教員の橋渡し的立場で、補佐的にかかわります。研修の記録は当センターで控え、次年度テーマ設定に役立てます。
1講師につき、一律10,000円となります。※定期の場合は1回毎に費用が発生します。
高崎市医療介護連携相談センター南大類
027-395-0102
027-395-0147
info@renkei-soudan.takasaki-u.ac.jp
(@は半角に読み替えてください。)
| 医療情報学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 木村 憲洋 | 病院との上手な付き合い方 | 介護の現場においては、医療機関はブラックボックスであり、わかりづらいものとなっています。そこで、病院の中の組織と病院における地域との連携における診療報酬や介護との関係にについて知識を習得することを目的とします。 |
| 社会福祉学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 金井 敏 | 民生委員・児童委員と福祉専門職の連携について | 民生委員・児童委員の役割は,住民の立場で支援を要する人や世帯を把握して,必要とする関係機関や専門職につなぐことです。福祉専門職として日常的にどのように連携すれば良いのか,民生委員・児童委員の職務からひもときます。 |
| 原田 欣宏 | 高齢者虐待防止の体制整備 | 高齢者虐待の事案が増え続けている現状から、すべての介護サービスに対して虐待の発生またはその再発を予防するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられました。この講座では高齢者虐待の知識や対応、高齢者虐待マニュアルを作成に役立つ情報について講義します。 |
| 岡田 哲郎 | はじめての地域アセスメント | 活動に先立つ地域社会の事前評価「地域アセスメント」の入門編として、ワークショップ体験を通じ、地域の特性と課題を捉える基本視点と方法を学びます。 |
| 健康栄養学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 竹内 真理 | 栄養アセスメント | 身体計測、生化学検査、臨床診査、食事摂取状況調査をとおした栄養状態の評価方法。 |
| 栄養ケア | 栄養状態不良と判定された患者の栄養管理。 必要栄養量の計算、栄養補給方法の決定、栄養療法の実施とモニタリング。 |
|
| 嚥下障害の食事 | 嚥下障害者の食事の工夫、嚥下訓練食。 | |
| 栄養剤の種類と選択 | 濃厚流動食の種類と特徴、病態に応じた濃厚流動食の選択。 | |
| 疾患別栄養管理 | 糖尿病、腎臓病、肝胆膵疾患、などの疾患別の食事療法と栄養管理 ※疾患を指定すればその疾患について詳しく講義する(糖尿病、メタボ、高血圧、透析等) |
|
| 老年期の栄養管理 | フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームなどの老年症候群の予防と改善。 | |
| 在宅一人暮らしの食事 | 独り暮らしの方の食事の注意点。調理、メニューの工夫など。 | |
| 曽根 保子 | 介護予防における食品選択のポイント | 介護予防という視点から、どのような栄養素が注目されているか、また、それらの栄養素を意識した食品選択についてお話いたします。 |
| 低栄養のリスクと栄養管理 | 高齢者における低栄養のリスクとその対策についてお話いたします。 | |
| 嚥下機能の評価について | 日常の生活のなかで、嚥下機能の低下に気付くためのチェックポイントと評価方法についてお話しいたします。 | |
| 大家 千枝子 | 身体活動の重要性再確認! ~まずは、動くこと、歩くことから~ |
車社会の群馬県では、移動手段の多くが車です。気がつけば、ほとんど歩かず、座っている時間が長くなりがちです。座ったまま体を動かさないと、いくつかの健康リスクが引き起こされることが明らかになっています。からだを動かす機会や環境は、身の回りにたくさんあります。それが「いつなのか?」「どこなのか?」。一緒に振り返りましょう。 |
| レクリエーションで心を元気に ~支援の理論と方法~ |
事情があって、身体を元気にできなくても仲間とともに身体を動かしながら、心豊かに過ごしたいと願う人は多いです。レクリエーションには、心を元気にする力があります。レクリエーション活動を有効に活用するための理論と方法を一緒に学びましょう。 | |
| 看護学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 田村 直子 | 意思決定を支える在宅療養支援 | その人にとっての最善とは何かを考えながら、在宅療養支援について事例を踏まえ、みなさんと考えていきたいと思います。 |
| 棚橋 さつき | 訪問看護とは | 訪問看護事業所の利用者は増加傾向ですが、訪問看護とはいったいどのような内容なのか。特徴は何か等基本的な事について。また今後の訪問看護のあり方について考えてみたいと思います。 |
| 退院支援の受け皿つくり | 医療依存度の高い療養者が在宅に帰る状況が増えています。 退院支援とは何か、地域で受け取る支援者はどのような準備をすればいいのか考えたいと思います。 | |
| 倉林 しのぶ | 医療・福祉における倫理 | 看護(介護)倫理とは何か、臨床や施設における倫理的課題への向き合い方、倫理カンファレンスの方法等について。 |
| 梅原 里実 | 認知症者及びご家族への対応 | 認知症者へ尊厳の保持を大切にした対応はケアの中心をなします。 また介護をするご家族の方が抱く困難を知ることはケアの工夫や広がりに繋がります。 |
| 理学療法学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 吉田 剛 | 相手の能力を引き出すトランスファーテクニック | 上手なトランスファー方法とは?相手の能力を引き出すことが自分の腰痛予防になります。実技練習を通して誰にでも身につけることができる手技を学びます。 |
| 誤嚥性肺炎を予防しよう | 誤嚥性肺炎を知り、予防に必要な知識を学びます。また、姿勢と誤嚥、嚥下機能低下に対するアプローチの実際を学びます。 | |
| 医療従事者の肩こりや腰痛を予防・改善しよう | なぜ肩こりや腰痛が発生しやすいか?日頃からできる予防法・対処法を学びます。 | |
| 篠原 智行 | 最近よくみる『フレイル』や『サルコペニア』とは? | 高齢者の『フレイル』や『サルコペニア』といった言葉を目にすることが増えてきました。これらの解説や、その対処方法をお話しさせて頂きます。 |
| 転びにくい体づくり、生活づくり | 転倒によって外傷や身体機能の低下を起こさないために、転倒の危険性の見分け方や転倒予防トレーニングをお話しさせて頂きます。 | |
| 高齢者の体力測定の実際と解釈 | デイサービスや通いの場などで、だれでも検査・測定ができる体力測定を、実践を交えてお話しいたします。測るだけではなく、その解釈も学びましょう。 | |
| 地域ケア会議をやってみよう | 各地で開催され始めた地域ケア会議。開催する準備のお手伝いから、参加者が地域ケア会議の実際を体験できる研修を一緒に考えましょう。 | |
| 薬学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 土井 信幸 | ポリファーマシーが高齢者のQOLに与える影響 | 多剤併用が高齢者のQOLへ与える影響とその回避方法。 |
| 高齢者が服用し易い薬とは? | 実際の薬剤を見て、触って、溶かして、高齢者にとって服用し易い薬について一緒に考える。 | |
| 在宅医療(地域連携)の中で薬のことで困ったら? | 地域の保険薬局、薬剤師の活用方法について。 | |
| 終末期における薬剤師の活用 | 終末期における緩和医療等に使われる薬剤の特徴と薬剤師の関わりについて。 | |
| 大林 恭子 | 経腸栄養と下痢・便秘 | 下痢と便秘について、特に経腸栄養を使用している場合を取り上げ、その原因と対処・治療についての話です。 |
| 子ども教育学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 野田 敦史 | 見守り支え合う共助社会の実現に 向けて -福祉ネットワークの視点から |
予防的福祉の観点から高齢者介護支援は、介護保険などのフォーマルサービスのみならず、地域ぐるみの住民参加によるインフォーマルサービスが必要不可欠である。本講では、福祉ネットワークの概念を用いて「子育てネットワーク実態調査結果」を紹介しつつ高齢者支援ネットワークへの援用を試みる。 |
| 五十嵐 一徳 | 発達障害のある方への関わり方 | 発達障害に関する基礎知識と対応方法について。 |
| 生物生産学科 | ||
|---|---|---|
| 担 当 教 員 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 岡田 早苗 | 日本の伝統発酵食品に秘められた植物性乳酸菌の機能性と活用 | 日本人の食形態はかつて一汁一菜でありました。これには「香の物(漬物)」が付くのが一般的でした。これらの食形態の中で健康保持に欠かせない乳酸菌との接点はあったのでしょうか。日本の伝統発酵食品をたどりつつ、旧来からあった日本人と乳酸菌との接点を探ります。 |
| 高崎健康福祉大学訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|
| 講 師 | タ イ ト ル | 概 要 |
| 佐橋 こずえ (看護師) |
在宅療養する小児の看護 | 地域で暮らす医療的ケア児やケアのない児(発達障がい、虐待など)とその家族支援について、また多職種との連携について。 |
| 新井 明子 (看護師) |
事例を通して考える神経難病療養者の在宅療養支援 | 神経難病療養者の療養支援は、病気の特徴を理解し、社会資源を活用しながら、チームで支援することが大切です。事例を通して、神経難病療養者の支援方法を考えたいと思います。 |
| 小林 綾作 (作業療法士) |
訪問リハビリテーション | 訪問看護ステーションのOTが現場でどんなリハビリを行っているのかを中心に事例や写真を通して紹介します。 |
| 高橋 典子 (言語聴覚士) |
高齢者の嚥下障害をみる時のポイント<施設編> | 高齢者の嚥下障害を施設でみる時のポイントについて。 |
| 高齢者の嚥下障害をみる時のポイント<在宅編> | 高齢者の嚥下障害について訪問でできる口腔・嚥下評価とリハビリについて。 | |
| ことばと飲み込みのためにできること | 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の方に実施する在宅でできるリハビリをご紹介します。 | |
| 摂食嚥下について学ぼう | 言語聴覚士に聞く摂食・嚥下の実際(低栄養と嚥下機能、肺炎予防と口腔ケア、完全側臥位での嚥下、パーキンソンの摂食嚥下、嚥下のリハビリ)。 | |
主に医療介護関係職種の方の相談をお受けしています。
相談への対応は看護師、保健師、社会福祉士がお答えします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
027-395-0102
9:00 ~ 17:00
土、日、祝祭日、年末年始はお休みとなります。
ご相談は看護師、保健師、社会福祉士がお受けします。

〒370-0036 高崎市南大類町200-2 2階
高崎健康福祉大学訪問看護ステーション内
027-395-0102 027-395-0147